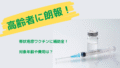「最近、帯状疱疹って増えてるって聞くけど…ワクチンで防げるの?」
そんなふうに思ったことはありませんか?
帯状疱疹は、加齢や体力の低下とともに、誰にでも起こる可能性のある病気です。
特に、50歳を過ぎた頃からリスクがぐっと高まると言われています。
帯状疱疹は痛みや皮膚の症状だけでなく、長引く神経痛(帯状疱疹後神経痛)が残ることもあり、早めの対策が重要です。
この記事では、看護師の立場から、帯状疱疹に関する情報を、やさしく、わかりやすくお伝えします。
「どうして帯状疱疹が起きるの?」
「どんな症状が出るの?」
「治療はどうするの?」
「予防はできるの?」
「ワクチンって本当に効果あるの?」
自分自身や家族の健康を守るために、ぜひ知っておきたい情報をまとめました。
看護師さん向けに詳しくまとめた記事はこちら
→ 増えている帯状疱疹|看護師が押さえておきたいポイントと患者ケア
帯状疱疹で一番怖いのは帯状疱疹後神経痛

帯状疱疹は、体の片側にチクチク・ピリピリとした痛みや違和感から始まることが多いです。
そのあと、赤みや小さな水ぶくれ(水疱)が、帯のような形であらわれてきます。
胸や背中、顔、腰まわりなど、左右どちらか一方に出るのが特徴です。
水ぶくれは数日から1週間ほどでかさぶたになり、皮膚の症状は2〜3週間ほどでおさまることがほとんどです。
しかし、人によっては痛みが強く出たり、皮膚が治ったあともピリピリ・ズキズキとした痛みが残ってしまうことがあります。
これを「帯状疱疹後神経痛(たいじょうほうしんごしんけいつう/PHN)」といいます。
特に、高齢の方ほど起こりやすい傾向にあります。
50代以上では約2割の方に帯状疱疹後神経痛が起こっています。
なかには、症状が悪化して入院が必要になったり、合併症が起きたりする可能性があります。
そのため、症状に気づいたら、早めに医療機関を受診することがとても重要となってきます。
合併症には次のようなものがあります。
- 結膜炎や角膜炎
- 耳鳴りや難聴
- 顔面神経麻痺
帯状疱疹は、できるだけ早く気づいて、できるだけ早く治療を始めることがとても大切なんです。
帯状疱疹の流行状況

帯状疱疹(たいじょうほうしん)は、ここ最近、特に50代以降の人に増えてきている病気です。
年齢を重ねるとともに、体の抵抗力(免疫力)が下がることが関係していて、今のような高齢化社会では患者さんが年々増えていると言われています。
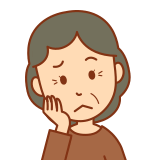
「なんだか脇腹がピリピリしてきて、水ぶくれみたいなものができたから病院に行ったら、帯状疱疹だったの…」
そんな話、あなたのまわりでも聞いたことはありませんか?
日本皮膚科学会によると、80歳までに3人に1人がかかるとも言われている帯状疱疹。
さらに最近では、新型コロナの流行や生活のストレスなども影響して、若い世代でも発症するケースがあると報告されています。
帯状疱疹発症が増加している4つの要因
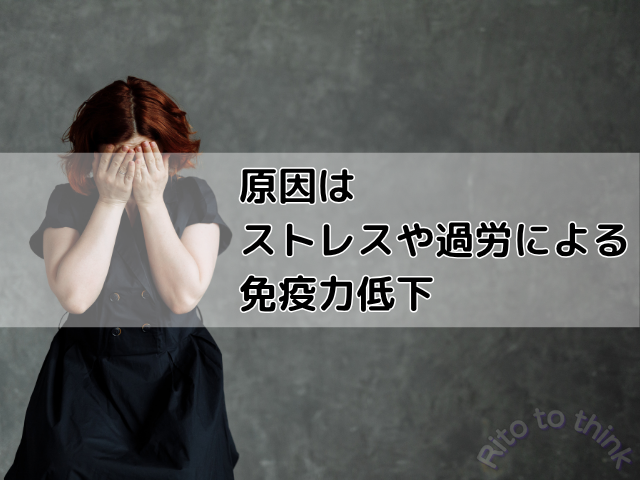
帯状疱疹は、「水ぼうそう」と同じウイルスが原因で起こります。
正式には「水痘・帯状疱疹ウイルス(VZV)」といって、子どもの頃に水ぼうそうにかかったことのある人の体には、このウイルスがずっとひそんでいます。
ふだんは何もせず静かにしていますが、年を重ねたり、疲れがたまったり、ストレスや病気などで体の免疫力(抵抗力)が弱くなると、ウイルスが再び動き出して、帯状疱疹としてあらわれることがあります。

では、どうして50代以上で帯状疱疹になる人が増えているのでしょうか?
4つの項目に分けてお話します。
高齢化社会と免疫力の低下
帯状疱疹が起こる大きな理由のひとつが、年齢を重ねることです。
年を取ると、体を守る働きをしてくれる「免疫力」が少しずつ弱くなっていきます。
若い頃はウイルスに対してしっかり戦えていた体も、年齢とともに免疫細胞の数が減ったり、働きが弱くなったりするため、眠っていたウイルスが再び動き出しやすくなるのです。
さらに、糖尿病などの持病を抱えている人も多くなり、これも免疫力を下げる原因になります。
こうした要素が重なって、50代以降に帯状疱疹が増えていると考えられています。
体調管理の一環として、免疫をサポートする成分を含むサプリメントを取り入れる人もいます。
例えば、キリン iMUSE ( イミューズ ) 免疫ケアやファンケル 免疫サポートなどがあります。
サプリメントは治療や予防を目的とするものではありません。
無理のない範囲で続けやすい方法のひとつとして、参考にしてみてはいかがでしょうか。
ストレスの増加
私たちの体には「自律神経」と呼ばれる働きがあり、その中に「交感神経」と「副交感神経」の2つがあります。
この2つのバランスがうまく保たれていると、免疫の働きもスムーズです。
でも、強いストレスや疲れが続くと、この自律神経のバランスが崩れてしまい、免疫力が下がってしまうことがあります。
免疫力が低下すると、体の中で静かにしていたウイルスが動き出し(=再活性化)、帯状疱疹として発症するリスクが高まります。
子どものワクチンと大人への影響
2014年から、子どもの水ぼうそうワクチンが定期接種として始まりました。
そのおかげで、水ぼうそうになる子どもはずいぶん減ってきています。
でも実は、それが大人の帯状疱疹が増えている理由のひとつではないかとも言われているのです。
一体どういうことなのでしょうか?
昔は、子育て中の親が、子どもから水ぼうそうウイルスを少しだけもらうことで、体の中の免疫がもう一度強くなる(これを「ブースター効果」といいます)ということが自然に起きていました。
これによって、大人の体の中に潜んでいたウイルスが再び活動しないように、免疫がしっかり働いてくれていたのです。
しかし、子どもたちがワクチンの効果で水ぼうそうにかからなくなったことで、大人がこうした追加の免疫刺激を受ける機会が減り、体の中のウイルスを抑える力が弱まりやすくなってしまったとも考えられています。
そのため、近年では50代以上の帯状疱疹が増加している背景に、この変化が関係している可能性があるのです。
健康意識の向上により病気に対する認識が増えた
最近では、テレビCMやメディアなどを通じて、「帯状疱疹」という病気の名前を知っている人が増えてきました。
そのため、「あれ?この症状はもしかして…」と気づいて、早めに病院を受診する人が多くなっています。
こうした健康意識の高まりも、帯状疱疹の患者数が増えているように見える理由のひとつだと考えられています。
帯状疱疹ってうつるの?
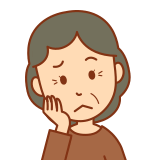
ウイルス感染だからうつるんでしょ?
感染したら帯状疱疹になっちゃうんよね?
そんなふうに思う方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、帯状疱疹そのものが他人にうつることはありません。
でも、ウイルス自体はうつることがあります。
なんか、こんがらがっちゃいますよね(笑)
帯状疱疹の発疹部分には、水ぼうそうの原因となるウイルスが含まれています。
そのため、まだ水ぼうそうにかかったことがない小さな子ども(乳幼児や小学生など)がこのウイルスに触れると、水ぼうそうとして発症する可能性があります。
これは、帯状疱疹と水ぼうそうが、どちらも同じ「水痘・帯状疱疹ウイルス(VZV)」によって起こる病気だからなんです。
帯状疱疹の発疹が治るまでは…
・水ぼうそうにかかったことがない人(特に乳幼児や妊婦)との接触を避ける
・発疹部分をガーゼや包帯で覆う
・タオルや入浴用品の共有を避ける
ちょっとした配慮で、まわりの人への感染リスクをぐっと減らすことができます。
帯状疱疹の治療
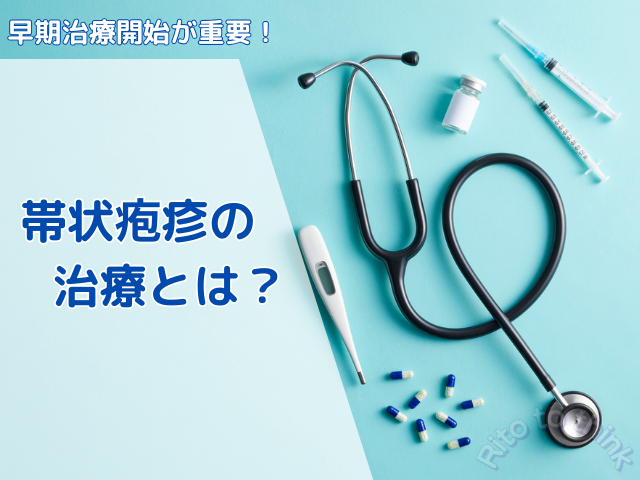
帯状疱疹は、できるだけ早く治療を始めることがとても大切です。
主な治療には抗ウイルス薬が使われます。
(例:バラシクロビル、アシクロビル など)
これらのお薬は、ウイルスの増える力をおさえて、症状を軽くしたり、治るまでの時間を短くしたりする効果があります。
できれば、発疹や痛みが出てからすぐに服用を始めることが望ましいとされています。
また、痛みが強い場合には、
・鎮痛薬(痛み止め)
・神経に作用する薬(例:リリカ/プレガバリン)
・神経ブロック注射 などが使われることもあります。
特に帯状疱疹の後に神経痛が残らないようにするためには、早めの受診と治療が重要です。
発疹がまだ出ていなくても、「なんだかピリピリする…」「触ると違和感がある…」と感じたときは、迷わず病院で診てもらいましょう。
家庭でできるケアと痛み対策

治療薬をもらって帰っても、残念ながらすぐに痛みは良くなりません。
家庭でできるケアをしながら帯状疱疹が良くなるのを待ちましょう。
また、すぐに受診できない場合など少しでも痛みが和らぐよう家庭でできるケアをご紹介します。
安静と休養
体をしっかり休めることで、免疫力の回復を助けます。
寝ている間も体はウイルスと戦っています。
十分な睡眠(免疫力を高めるために7時間以上)と栄養をとり、精神的・肉体的な安静を心がけましょう。
水ぶくれを破らない
水ぶくれが破れると、細菌による感染が起こりやすくなります。
細菌による化膿(かのう)を防ぐためにも、患部は触らないようにしましょう。
皮膚の清潔を保つ
患部を清潔に保ち、かゆみがあってもかかないよう注意しましょう。
皮膚が清潔に保たれていないと、水ぶくれが破れてしまった時に細菌感染を起こしやすくなります。
衣類の工夫
ゆったりとした柔らかい服を選ぶと刺激を減らせると同時に、衣服による摩擦も少なくなるので水ぶくれが破れる危険性も少なくなります。
温める
これは意外に思う方も多いはず。
皮膚がピリピリするので冷やしたら痛みが和らぐんじゃないか?と思いがちですが、冷やしてはいけません。
皮膚が冷えると血管が縮み、血流が悪くなり感覚が過敏になりやすくなります。そのため痛みを感じやすくなります。
患部は冷やさずに、できるだけ温めて血行をよくしましょう。
使い捨てカイロや温シップ薬を使うのもいいですが、やけどやかぶれに注意が必要です。
温かいタオルを当てるのもおすすめです。
高熱がなければ、温めのお風呂にゆっくりと浸かりましょう。
市販薬の使用について
基本的には医師から処方された痛み止めを内服しましょう。
市販の痛み止めを使う場合は、医師や薬剤師に相談を。
飲酒を控える
お酒類を飲むと、血管が広がり炎症や痛みを悪化させる可能性があります。
また、お酒の飲み過ぎは免疫力を低下させると言われていますので帯状疱疹が治るまでは飲酒を控えるようにしましょう。
予防接種について

帯状疱疹に対してワクチン接種は予防効果が高いと言われています。
日本で現在承認されているのは、50歳以上の方を対象とした2種類のワクチンです。
生ワクチン(乾燥弱毒性水痘ワクチン)
・1回の接種でOK
・効果の持続はおよそ5年程度とされています
・比較的費用が抑えられます
不活化ワクチン(シングリックス)
・2回の接種が必要(2か月間隔)
・予防効果が高く、持続期間も長いとされています
・副作用がやや出やすい
・費用が高め
どちらのワクチンにもそれぞれ特徴や注意点があるため、年齢や体調、持病などに応じて選ぶ必要があります。
気になる方は、かかりつけの医師に相談してみるのがおすすめです。
帯状疱疹ワクチンの比較表
| 種類 | 生ワクチン (乾燥弱毒性水痘ワクチン) | 不活化ワクチン (シングリックス) |
|---|---|---|
| 接種回数 | 1回 | 2回(2か月空けて2回接種) |
| 予防効果 | 中程度(60%前後) | 高い効果(90%以上) |
| 効果の持続期間 | 約5年程度 | 9年以上持続するとされる |
| 副作用の出やすさ | 少なめ | やや出やすい |
| 費用(目安) | 比較的安価(数千円〜) | 高め(2回で約4〜5万円程度) |
| 接種対象 | 50歳以上 | 50歳以上(特に重症化リスクのある方に推奨) |
| 公費助成 | 一部自治体であり | 一部自治体であり |
※費用や助成制度については、お住まいの自治体や医療機関によって異なります。接種を希望する場合は、かかりつけ医や市町村に確認してみてくださいね。
帯状疱疹ワクチンの公費補助

これは朗報です!
2025年4月から、帯状疱疹のワクチンが定期接種の対象となり、65歳以上の方には公費補助が始まりました。
対象は、
・2025年度に65歳になる方
・60〜64歳で特定の免疫低下状態にある方
・2025〜2029年度に70・75・80・85…100歳になる方も順次対象(経過措置)
自分は対象年齢じゃないから関係ないな、と思っている方いませんか?
いいえ、自分は対象じゃなくても周囲の方に声をかけてあげることはできます。
ご両親や親戚のおじさんおばさんなど、対象年齢に当たる方がいれば声をかけてあげましょう。
対象の方には、自治体から接種券や案内が送られてくる場合があります。
気になる方はお住まいの市町村に問い合わせてみましょう。
自治体によっては50代〜でも補助あり!
定期接種の対象外でも、独自の助成を行っている自治体も増えています。
こういった助成制度を活用すれば、自己負担をかなり抑えて接種することができます。
確認は、お住まいの自治体のホームページ、保健所や市役所の窓口へ。
かかりつけ医に相談してみるのも◎
まとめ:帯状疱疹は予防と早期対応がカギ

帯状疱疹は、加齢などによって誰にでも起こる可能性のある、身近な病気です。
でも実は、ワクチンで予防できる可能性が高い病気でもあります。
もちろん、ワクチンを接種したからといって100%発症しないわけではありません。
それでも、発症や重症化を防ぐ有効な手段のひとつであることは確かです。
正しい知識を持ち、早めに対処すること。
そして、必要に応じて予防接種を検討すること。
この2つが、帯状疱疹による重症化や後遺症を防ぐカギになります。
「これってもしかして…?」と感じたら、迷わず受診を。
また、50代以上の方は、ワクチン接種についても一度検討してみると安心です。
今回は、近年増えつつある帯状疱疹についてお伝えしました。
お金も大事だけど健康も大事。
健康資産を守って、これからも自分時間を大切に楽しんでいきましょう。
また暮らしに役立つ情報をお届けしていきますね。
読んでくださってありがとうございました!
ーときどきナースのりとしんくでしたー